親の土地に自分の家を建てた後のリスク回避の方法
前回、親の土地に子どもが家を建てた後、トラブルの原因になる理由について説明しました。
今回はそのトラブルを回避するにはどの様な方法があるのかについてです。
土地代を払っていても問題があります
例えば親に権利金を支払い、相応の土地代を毎年支払っていく場合はどうでしょうか?
親子の関係でも借地権は成立しますから、権利上の問題はなさそうです。
ところがそれから数年後に親が亡くなれば、今度は兄弟姉妹の不満が爆発することになりかねません。
たとえば1憶円の評価の土地に対して1千万円の権利金を支払い、1年後に親が亡くなったとします。
このとき
「借地権が有効だから、自分には7千万円分の権利がある」
と主張しても、他の兄弟姉妹が簡単に納得することはないでしょう。
一人っ子だから大丈夫、ではありません
上記ではとりあえず母親の存在は別にして兄弟姉妹間の争いを想定しましたが、それなら
「一人っ子だったら問題ない」
というわけではありません。
たとえば親の土地に家を建て、妻と子どもと自分の両親の二世帯で暮らしていたとします。
このとき自分自身が不慮の事故で亡くなったとすれば、家は妻子が相続するものの、その敷地は引き続き親のものです。
「妻子に家を残してやった」
などと草葉の陰で喜んでいる場合ではありません。
妻からすれば亡くなった夫の両親と同居することの落ち着かなさ、両親からすれば嫁と孫が所有する家に暮らす気まずさも生まれるでしょう。
これが使用貸借であれば、家を売却してそれぞれの生活を再スタートさせようとしても、売却代金について妻の取り分がないこともあり得ます。
このリスクを減らすにはどうすればいいのか
ここで取り上げたようなトラブルは、これから数十年経っても日本のどこかで起き続けるに違いありません。
親の土地に家を建てるときのリスクを減らし、税法上も有利なようにするためには、親に代金を支払って土地の持分を手に入れたり、家の持分と交換したりすることが一つの方法です。
また、贈与の特例などを組み合わせることも考えられます。
しかし、持分を買い取るための資金や、贈与の場合に他の兄弟姉妹との均衡をどう保つかなど、いろいろと問題が生じることも多いはずです。
実際にどうするのが良いのかは、親が持つ土地以外の資産によって大きく変わる場合もあります。
できれば事前に専門家のアドバイスなどを受ける事をオススメします。
それと同時に、他の兄弟姉妹との十分な話し合いも大切であることは言うまでもありません。
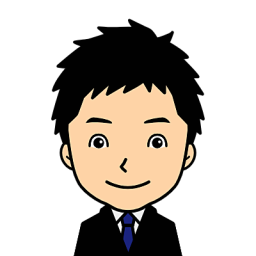
関連した記事を読む
- 2025/05/19
- 2025/05/13
- 2025/05/07
- 2025/05/02















お客様に対して、不動産に関する複雑な内容でも、少しでも分かりやすくご説明できるよう日々努めております。